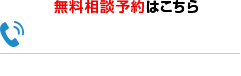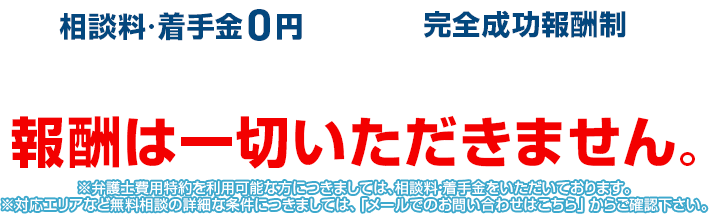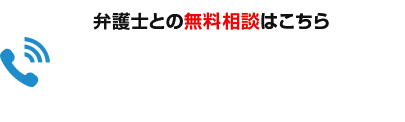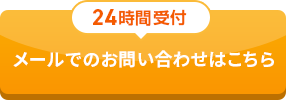付添看護費とは?
付添看護費とは,交通事故の受傷で被害者に介護・介助が必要な場合に認められる損害のことをいいます。
職業付添人や近親者が付添った場合に,必要かつ相当な限度で認められています。
なお,近親者が付添った場合,実際に近親者へ対価を支払うことは付添看護費請求の前提とはなっていません。
判例(最三小判昭和46年6月29日民事判例集25巻4号650頁)は,「現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙つたものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができる」と判断しました。
また,判例では,近親者の損害ではなく,被害者本人の損害として計上されています。
最三小判昭和46年6月29日民事判例集25巻4号650頁
被害者が受傷により付添看護を必要とし、親子、配偶者などの近親者の付添看護を受けた場合には、現実に付添看護料の支払いをせずまたはその支払請求を受けていなくても、被害者は近親者の付添看護料相当額の損害を蒙つたものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するを相当とする。けだし、親子、配偶者などの近親者に身体の故障があるときに近親者がその身のまわりの世話をすることは肉親の情誼に出ることが多いことはもとよりであるが、それらの者の提供した労働はこれを金銭的に評価しえないものではなく、ただ、実際には両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には肉親たるの身分関係に基因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではなく、被害者は、近親者の付添看護料相当額の損害を蒙つたものとして、加害者に対してその賠償を請求することができるものと解すべきだからである。
付添看護費の種類
付添看護費は,大きく分けると以下のように分類できます。
| 症状固定前 | 入院付添費 | 交通事故で入院した被害者に職業付添人ないし近親者が付き添った場合の付添看護費 |
|---|---|---|
| 通院付添費 | 通院に近親者が付き添った場合の付添看護費 | |
| 症状固定までの自宅付添費 | 自宅療養するに際して,日常生活上介護を受ける必要がある場合の付添看護費 | |
| 固定後 | 将来付添費(将来介護費) | 重度後遺障害等により症状固定後も介護が必要な場合の付添看護費 |
入院付添費
入院付添費は,入院中の付添いの必要性がある場合に,相当な限度で認められています。
一般的には医師の指示がある場合に付添の必要性が認められますが,それ以外でも,受傷の程度,被害者の年齢等に応じて認められています。
医療機関において基準看護(いわゆる完全看護)体制が取られている場合には,通常医療機関から近親者の付添を求められることは無く,付添看護の必要性についての証明(医師の指示)が得られないことがあります。
被害者が入院した医療機関で基準看護体制が取られていることを理由に,保険会社が付添看護費の支払いを拒むケースは多く見られます。
しかし,医療機関が基準看護体制を取っているか否かは,患者数に対する看護師数で決まる形式的な問題です。
現実には,基準看護体制が取られている病院においても,24時間看護師が付き添っての看護が保障されているわけではありません。
そのため,医師の指示がない場合であっても,被害者の症状が重篤であったり,年少者,高齢者等の場合には,近親者による付添看護の必要性が認められることがあります。
例えば,大阪地判平成27年7月2日 交通事故民事裁判例集48巻4号821頁では,完全看護体制が取られている上,個室利用について医師の指示がなかった事案ですが,咀嚼機能障害で治療のために口をワイヤーで固定され,筆談でやりとりをし,食事も流動食であったこと等から,近親者付添の必要性・相当性が認められています。
裁判例では,重篤な脳損傷や脊髄損傷,上肢下肢の骨折等で身体の自由がきかない場合や,幼児・児童の場合に付添費用が認められやすい傾向にあります(日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)26訂版15頁)。また,近親者の付添が被害者の回復のために必要であったり,一定の効果が認められる場合にも,付添費用を肯定する例が見られます。
職業付添人を雇った場合には,原則的には実費全額が認められるものと考えられています(青本26訂版15頁。日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)の基準も同じ)。
近親者の付き添いの場合は,日額5,000~7,000円程度(青本26訂版15頁。なお,赤い本では6,500円,大阪地裁では6,000円)が目安ですが,被害者の症状が極めて重篤であったことから日額8,500円の付添費を認めた裁判例(仙台地判平成21年11月17日交通事故民事裁判例集42巻6号1498頁)等もあります。
近親者が付添看護のために仕事を休んだ場合は,近親者の休業損害の日額が定額の近親者付添費より多ければ,近親者の休業損害相当額が付添看護費の金額として認められています。
例えば,福岡地判平成25年7月4日判例時報8229号41頁では,近親者の給与収入を参考に,日額1万円の近親者付添看護費が認められています。
もっとも,休業による損害が職業付添人の付添費を上回る場合には,職業付添人を雇うべきですから,職業付添人の付添費が限度になると考えられます。
大阪地判平成27年7月2日 交通事故民事裁判例集48巻4号821頁
(2) 個室代 57万円
原告本人尋問の結果等によれば,入院先の日赤医療センターでは完全看護の体制が取られていた上,個室の利用について医師の指示があったわけではない。しかし,原告は,治療のために口をワイヤーで固定されていたため,話すことができず文字で◯らとやり取りをしており,また,食事も流動食が続いていたというのであり,原告の置かれたこのような状況や,けがの内容・程度,さらには,治療の内容と原告の精神的負担の大きさなども考慮すると,個室の病室を選択することはやむを得ないといえ,個室代は,その額を含めて必要かつ相当なものと認められる。
︙
(5) 入院付添費 19万円
上記のような入院中の原告の状況等に照らすと,完全看護の体制が取られていたとはいえ,◯の付添いは必要かつ相当なものと認められる。必要な付添いの程度等に照らすと,日額5000円を認めるのが相当であり,本件事故と相当因果関係のある1回目の入院期間について,以下の計算式により損害として認められる。
(計算式)日額5000円×38日=19万円
通院付添費
入院付添費と同様に,被害者の症状や年齢等により,近親者の通院付添の必要がある場合,通院付添費として日額3,000~4,000円程度(青本26訂版15頁。なお,赤い本では3,300円,大阪地裁では3,000円)が認められています。
具体例としては,下肢の骨折で歩行困難であったり,高次脳機能障害で単独での通院が困難な場合,一人で通院できない幼児・児童の場合などが考えられます。
症状固定までの自宅付添費
退院後,症状固定までの自宅療養中に,身の回りの世話,介助,看視,声掛けなど日常生活上介護を受ける必要があるような場合に,自宅付添費が損害として認められています。
自宅付添費については,入院の場合と比較して負担が少なかったり,拘束時間が短いような場合には,事案に応じて入院付添費の範囲内で算定することになると考えられます(佐久間邦夫=八木洋一編「リーガル・プログレッシブ・シリーズ5 交通損害関係訴訟[補訂版](青林書院2013年)」134頁)。
実際の自宅付添費の金額については,入院付添費よりは低額になる場合が多いとの指摘があります(青本26訂版15頁)
将来付添費(将来介護費)
重度後遺障害により症状固定後も付添介護が必要な場合,その後遺障害の内容や程度,介護の負担などに応じて将来の付添費用(将来介護費)が認められます。
自賠責施行令別表で介護を要する後遺障害として明示されているのは別表第1の1級(常時介護)及び2級(随時介護)のみですが,裁判実務ではこれら以外の後遺障害についても,介護の必要性がある場合には将来介護費が認められています。
将来介護費を一時金で受け取る場合には,中間利息を控除して以下のように算定されます(中間利息控除やライプニッツ係数の意味については,「後遺障害の逸失利益」の用語説明を参照下さい)
将来介護費の日額✕365(日)✕平均余命に対応するライプニッツ係数
近親者による場合
近親者の将来介護費の場合は,常時介護(1級)の場合で日額8,000~9,000円が目安とされています(青本26訂版22頁。なお,赤い本及び大阪地裁では8,000円)。
一方,常時介護を必要としない場合には,介護の必要性の程度,内容によって減額されることがあるという指摘があり(青本26訂版22頁),随時介護(2級)の事案で一定金額を減額する裁判例が多く見られます。
そして,身体介護を要せず,看視,声掛けで足りる場合は,一般に身体介護よりも肉体的な負担が軽いことから,身体的介護が必要な場合よりも低額の介護費が認定されています。
職業付添人による場合
介護を必要とする程度や現在の介護状況,家族状況などから,職業付添人の介護の必要性及び職業付添人による介護の蓋然性(現在職業付添人を利用していないが,将来利用予定である場合に,職業付添人介護の蓋然性が大きな争点となります)が認められる場合には,職業介護人の介護費用が認められています。
職業付添人を雇った場合には原則実費全額が認められると考えられていますが(赤い本の基準),実際の裁判例では,12,000~20,000程度の認定例が多いという指摘があります(北河隆之「交通事故損害賠償法[第2版]」弘文堂2016年124頁)。
また,最近の傾向として,現在は近親者の介護が行われていても,近親者が老齢化した場合には職業付添人による介護に移行することを前提に将来介護費を認定する例が増えているという指摘があります(青本26訂版23頁)
例えば,大阪地判平成26年12月8日交通事故民事裁判例集47巻6号1475頁では,頸髄損傷等の後遺障害を負った事案について,主に介護している近親者が67歳になるまでは日額8,000円,67歳以降は被害者の平均余命まで日額20,000円が認定されています。
大阪地判平成26年12月8日交通事故民事裁判例集47巻6号1475頁
オ 症状固定後の将来介護費 8236万7214円
(ア) 原告△が67歳になるまでの将来介護費
上記(1)アの原告◯の症状固定後の状況並びに上記(1)イ及びウの原告◯の症状固定後の介護の状況に鑑みれば,原告◯は,日常生活に必要となる多くの動作について介護を要する状態であることが認められるが,他方で,意識清明で会話をすることができ,緊急の必要等があればその都度連絡等することも可能であること,また,自宅で車いすを使用して自走することや専用のフォーク等を使った食事をすることは可能であることが認められる。そして,現在,原告△を中心とする近親者介護が主にされており,それとともに,一定程度職業介護人による介護がされていることに鑑みると,原告△が67歳になるまでは,このような介護体制が継続されることを前提として介護費を算定するのが相当である。
以上の介護体制,上記(1)ウより認められる必要な介護の内容,下記カのとおり本件訴訟によって賠償が認められるべき福祉用具の内容,上記(1)オの職業介護人による介護に要する費用と自己負担額等を総合考慮すると,原告△が67歳になるまでの将来介護費としては,原告◯が入院していた間や職業介護人による介護が現在よりも少なかったときも含めて,日額8000円として算定するのが相当である。
そして,弁論の全趣旨によれば,原告◯の症状固定時,原告△は47歳であったから,原告△が67歳になるまでの将来介護費は,下記の計算式のとおり,3638万9624円となる。
【計算式】
8000円×365日×12.4622=3638万9624円
(イ) 原告△が67歳になった後の将来介護費
原告△が67歳になった後は主に職業介護人による介護が行われることが想定されるところ,その介護体制,上記(1)ウより認められる必要な介護の内容や程度,下記カのとおり本件訴訟によって賠償が認められるべき福祉用具の内容,上記(1)オの職業介護人による介護に要する費用と自己負担額等を総合考慮すると,原告△が67歳になった後の将来介護費は,日額2万円として算定するのが相当である。
そして,原告◯は,症状固定時23歳であり,23歳男性の平均余命は57年であるから,原告△が67歳になった後の将来介護費は,下記の計算式のとおり,4597万7590円となる。
【計算式】
2万円×365日×(18.7605-12.4622)=4597万7590円
(ウ) 合計
以上より,将来介護費は,上記(ア)及び(イ)の合計額8236万7214円となる。
公的扶助・公的サービスとの関係
将来受給できる介護保険給付等ついては,将来も現在と同様の給付の内容及び水準が維持されるかどうかが不確定であることから,多くの裁判例で損益相殺が否定されています(Q介護保険給付は賠償金から差し引かれるのでしょうか?)。
同様に,将来介護費の算定事情としても斟酌されないものと考えられます。