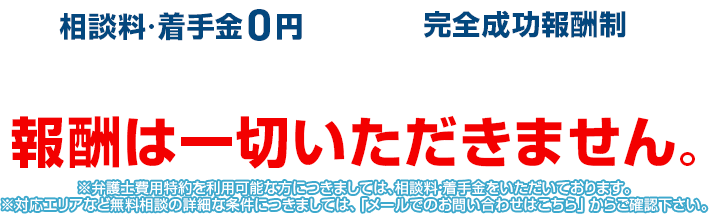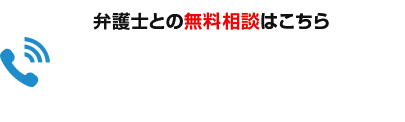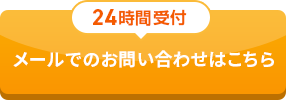休業損害とは
休業損害とは,怪我をしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに生じた収入の減少のことです。
特に,貯蓄が少ない人や一人暮らしで毎月賃料を払って生活している人,ローンの返済がある方などは,仕事ができずに収入が途絶えると,日常生活に大きな支障が生じるので,休業損害が生じるような場合は,専門家である弁護士に相談して,適正な金額を請求するとよいでしょう。
休業損害の具体的な計算方法は職種等により異なるので,ここでは給与所得者について説明します。
給与所得者の休業損害
給与所得者の休業損害は,事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減を填補する範囲で認められます。具体的には,交通事故で傷害を負ったことを原因として休業した場合に,その休業によって現実に収入が減少した額(減収額)が損害として認められるのが原則です。
事故前の3ヶ月間の給与額の合計を90日で割って基礎収入(日額)を算出し,それに休業期間を乗じて算定するのが保険会社における一般的な損害算定方法です。
基礎収入とは,事故前の収入のことをいい,通常,交通事故の3ヶ月前からの給与が算定基礎になります。しかし,給与が大きく変わるような職種の場合は,前年度の収入や長期間の収入を基礎として計算する場合もあります。
保険会社に休業損害を請求する場合の実務の運用上では,勤務先会社に「休業損害証明書」を作成してもらい,これを基礎収入の根拠とするのが一般的です。
上記のように,給与の大きな変動があった場合のように,事故前3ヶ月の収入を基礎収入とするのが適当でないような事情がある場合は,被害者の側で別途の基礎収入の基準を用いて計算すべきとする理由を主張・立証していく必要があります。
前述のとおり,実務では,通常,日額については90日で割って計算されています。
しかし,この日額算定方法に関しては,休業期間が連続していない場合,単純に90日で割って日額を計算することがはたして合理的かについて疑問があります。
なぜなら,雇用契約上,月収には休日に働くことは反映されておらず,休日に働く場合,別途休日出勤手当などが加算されることが一般的だからです。
このように,月収に休日分の給与額が反映されていないにもかかわらず,日額給与額を計算する際に,月収を休日が含まれた歴日数で割る計算方法をとると,被害者にとっては不利な結果になります。
この問題について,武富一晃裁判官の講演録「給与所得者の休業損害を算定する上での問題点(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 平成30年度版下巻収録)」では,継続しての完全休業ではなく,就労しながら一定頻度で通院を行っている場合で,事故前の具体的な稼働日数,支払いを受けた給与の金額を証拠上認定できる場合には,休日を含まない実労働日1日あたりの平均額を基礎収入とする方法が相当だと指摘されています(同講演録38~39頁)
名古屋地判平成26年5月28日自保ジャーナル1926号144頁では,「基礎収入は,本件事故前3か月間の収入56万2215円を稼働日数62日で割った9067円とする」として,実稼働日で除した額を日額として休業損害が計算されています。
大阪地判平成30年12月21日(平成28年(ワ)第12442号)でも,事故前年総収入と事故年総収入との差額を休業損害とする原告主張と,事故前3ヶ月収入を90日で割った基礎日額8582円をもとに休業損害を算定した被告主張を両方とも採用せず,実稼働日で除した額を日額として休業損害が算定されています。
また,東京地判平成23年2月8日自保ジャーナル1849号125頁でも,「欠勤日が連続していない場合等で,当該欠勤日にのみについて休業損害が発生したとして算定するときは,実労働日1日あたりの平均額を算出するほうが妥当な場合であることが多いであろう。」と判示され,欠勤日が連続していない場合に稼働日で割る方法が妥当であることが示されています。
これらの裁判例を見るかぎり,保険会社が示談交渉段階で譲歩するかどうかは別として,訴訟に移行すれば,稼働日で割って日額を計算する方法が認められているように思います。
名古屋地判平成26年5月28日自保ジャーナル1926号144頁
(7) 休業損害 55万3087円(請求:58万0288円)
ア 原告の主張
本件事故前3か月間の収入は56万2215円,稼働日数は62日であり,退職前に61日休業したほか,3日の入院期間中はいかなる業務に従事することも不可能であったから,休業日数は64日となり,58万0288円の休業損害が認められるべきである(56万2215円÷62日×64日)。
イ 被告らの主張
収入日額は91日で除した額とすべきである。入院時には既に退職しており,休業日数は61日である。
ウ 判断
基礎収入は,本件事故前3か月間の収入56万2215円を稼働日数62日で割った9067円とする。現実に減収の発生が認められるのは,Bの休業61日分であり,休業損害は55万3087円(9067円×61日)を認める。
大阪地判平成30年12月21日(平成28年(ワ)第12442号)
ウ 休業損害 70万5105円
(ア) 基礎日額 1万1882円
(54万0600円(本給)+23万1788円(付加給))÷65日(稼働日数)=1万1882円(1円未満切捨て)
休業損害の時間的範囲
休業損害が認められるのは,傷害が完治するか,症状固定日までとされています。症状固定日後も休業している場合は「後遺障害逸失利益」の問題となるので,休業損害とは別の費目で評価されることになるので注意が必要です。
なお,交通事故による傷害を理由として休業したのであれば,有給休暇を使用したときも休業損害と認められます。交通事故のせいで,本来ほかに利用できた有給休暇を使用しなければならなかったと考えられるからです。
しかし,休業損害は実損害なので,怪我をしても頑張って勤務を続けたという場合は,仮に休んでいたら発生したであろう休業損害を認めてもらうことはできないのが原則です。但し,会社の状況上簡単に休むことができずに頑張って仕事をしたが,「本来は休業すべき程度の症状だった」ことが証明できれば,傷害慰謝料(入通院慰謝料)の増額事由として考慮される場合もありえます。
休業損害が認められる例外的ケース
休業はしていなくても,残業を減らさざるを得なくなって収入が減ったようなケースでは,現実の収入減が発生しているので,休業損害として認められる可能性があります。
反対に,休業損害が実損害であることから,休んだ方が得だとして,多少のケガで休んだ場合には,受傷・症状の内容・程度や治療経過等から就労可能であったと認定されると,現実に休業して収入減が発生していても休業損害として賠償の対象とならない場合もありえます。
また,休業損害の範囲は,休業期間だけではなく,休業によって実質的にこうむった損害も含まれます。
具体的には,休業したために賞与が減った場合も休業損害の対象となります。この場合,勤務先の会社に「賞与減額証明書」を作成してもらうなどして主張・立証していくことになります。