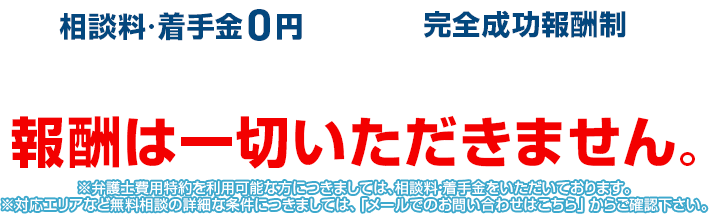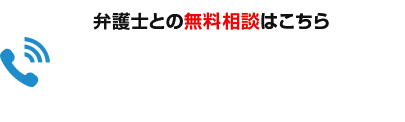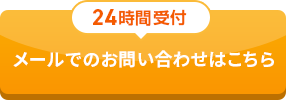退職と事故との間に相当因果関係があるか
事故後被害者が症状固定前に退職した場合,症状固定までの休業損害は認められるのでしょうか。
退職が事故に起因すると認められ,かつ,症状固定前まで再就職することが困難であると認められる場合には,症状固定日までの休業期間が認められます。
一方,再就職可能であったと考えられる場合には,再就職が可能と判断される時期までの休業期間が認められています。
そして,退職と事故との因果関係が認められない場合は,退職後については休業期間として認められないことになります。
自主退職扱いに注意
事故による怪我以外の原因で退職した場合,退職後の減収は事故と因果関係のある損害とは言えません。
そのため,退職理由は因果関係の認定に影響を及ぼすものといえます。
非常に悪質ですが,後日解雇の有効性を争われることを懸念して,解雇をせずに強引な退職勧奨を行い,自ら退職願を提出させて自主退職扱いにするケースも見られます。
このような場合,会社側は違法行為になりうることを十分に認識しているため,退職勧奨の言動や実質的な解雇の通知等については一切書面に残さず,口頭で済まそうとするでしょう。
そうすると,被害者としては,事故が原因で会社に事実上解雇されたと主張したくても,利害関係人である被害者本人の供述しか退職勧奨行為等の証拠がなく,書類上は退職願が会社に提出され,離職票上も自主退職扱いになっているため,退職が事故に起因するものだと立証することが難しくなります。
事故による受傷が原因で退職を余儀なくされた場合,解雇が有効か無効かの問題は別途ありますが,退職後の休業損害の認定に関わる部分ですので,自主退職ではなく,会社都合退職と離職票の離職理由に記載してもらう必要があります。
後遺障害の程度と因果関係の認定
本件と同様に,事故と退職との間の因果関係が問われる場面として,退職金差額(Q事故がなければ貰えたであろう退職金は請求できるのでしょうか?)の問題があります。
川﨑直也裁判官の講演録「退職金差額請求について」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 平成24年版下巻収録)では,死亡事案や労働能力喪失率が100%である事案では通常問題になることはなく,労働能力喪失率79%以上(後遺障害1~5級)といった重度の後遺障害の場合にも,従事可能な職務が非常に限定されることから一般的に退職との因果関係が認められるが,後遺障害の程度が重度とまでは言えない場合については,次の①~③の要件を全て満たすときに限って因果関係が認められるべきで,特に労働能力喪失率20%以下(後遺障害11~14級)の軽度の後遺障害事案では,因果関係を肯定するのは難しいと指摘されています。
この川﨑裁判官の指摘は,本件の因果関係の認定においても参考になると考えられます。
①後遺障害の内容・程度が被害者の職務に直接関連している
② ①の影響が強いために,職務を継続するのが困難
③被害者の職種及び勤務先の状況から配置転換等によって退職を回避するのが困難
裁判例
退職後症状固定までの期間について休業損害が認められた事例として,さいたま地判平成25年4月16日交通事故民事裁判例集46巻2号539頁があります。
さいたま地判は,左下肢の欠損等で併合4級の後遺障害を負った団体職が職場復帰後5年9ヶ月後に退職し,その1049日後の症状固定時においても再就職できなかった事案について,退職前後の期間で入院・皮膚移植を繰り返していること等から事故受傷と退職との因果関係を認め,退職から症状固定までの全期間について休業損害を認めました。
一方,東京地判平成21年8月25日(平成20年(ワ)第34176号、平成21年(ワ)第1511号)では,事故と退社との因果関係を認めるに足りる的確な証拠はないとして,因果関係が否定されています。
さいたま地判平成25年4月16日交通事故民事裁判例集46巻2号539頁
(4) 休業損害
ア 証拠によれば,原告は,本件事故前に社団法人◯協会に業務課長として勤務し,本件事故前年に531万6000円(日額1万4564円)の収入を得ていたこと,平成11年3月9日から平成12年2月29日までは,上記仕事を完全に休業していたこと,同年3月1日から平成17年12月31日(退職日)までの間の欠勤又は有給休暇取得日数が135日であること,平成18年1月以降,再就職できていないことが認められる。
イ 前記ア認定事実によれば,休業損害は次のとおり認められる。
(ア) 平成11年3月9日から平成12年2月29日まで(358日間)
約1年の休業期間であることに鑑み,本件事故前年の収入を基に日額1万4564円の休業損害の発生を認めるのが相当である。
(イ) 平成12年3月1日から平成17年12月31日(退職日)まで
欠勤又は有給休暇取得日数135日について,上記の日額1万4564円の割合による休業損害の発生を認めるのが相当である。
(ウ) 平成18年1月1日から平成20年11月14日(症状固定日)まで
前記(1)の治療経過,原告の症状及び就労内容に照らせば,本件事故による受傷と原告が退職したこととの間には相当因果関係が認められる。その後,原告が再就職できていないことに照らし,上記期間の1049日について日額1万4564円の割合による休業損害の発生を認めるのが相当である。
(エ) したがって,日額1万4564円の割合により合計1542日につき休業損害が認められるので,その額は2245万7688円である。
東京地判平成21年8月25日(平成20年(ワ)第34176号、平成21年(ワ)第1511号)
証拠によれば,亡◯は,本件事故前の平成17年3月及び4月当時△社に勤務し,稼働日数27日で計18万6458円(日額平均6906円)の収入を得ていたもので,本件事故による傷害のために,平成17年4月23日から同年6月15日までの間に28日間休業を余儀なくされたほか,平成17年度の夏期賞与を3万7574円減額されたことが認められる。したがって,亡◯の休業損害の額は,次の計算式のとおり,23万0942円となる。
〈計算式 6,906×28+37,574=230,942〉
これに対し,被告らは,亡◯の就労不能期間は本件事故日から30日を経過した平成17年5月18日までであり,それを超える休業は亡◯の労働意欲が乏しかったからに過ぎない旨主張するが,前記亡◯の傷害の内容,程度及び治療経過に照らし,亡◯が△社を退社した平成17年6月15日までの休業の主たる原因が亡◯の労働意欲が乏しいことにあったとまでは認められないから,上記被告らの主張は採用できない。
なお,原告らは,亡◯が△社を退社した後平成18年9月7日までの期間についても休業損害が生じた旨主張するが,本件事故と△社の退社との因果関係を認めるに足りる的確な証拠はない上,別の会社への再就職後は休業の事実自体が認められず,当該期間中の収入額や具体的な就業状況も不明であるから,上記原告らの主張は採用できない。