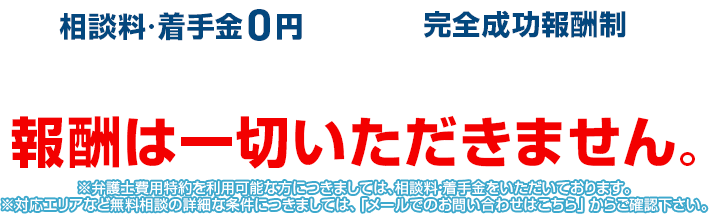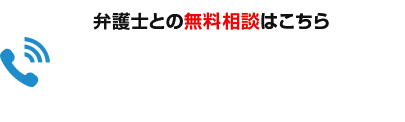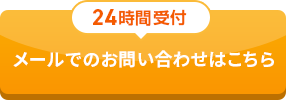京都地判平成12年3月23日判例時報1758号108頁
争点
22歳医学生の死亡事故において、67歳を超える就労可能期間の終期が認められるかが争点となりました。
判決文抜粋
1 原告らの主張
︙
② 就労可能期間の終期 七五歳
ア 財団法人厚生統計協会発行の「国民衛生の動向(平成五年版)」によれば、女性の平均寿命は平成四年には八二・二二歳であり、平成七年簡易生命表によれば、二二歳女子の平均余命は六一・五〇年である。
◯は、本件事故がなければ、平均余命六一・五〇年の八〇ないし九〇パーセントの期間、医師として仕事をなし得た。
したがって、
二二歳+(六一・五〇年×〇・八~〇・九)=七一・二~七七・三五歳
となり、平均は七四・二七五歳となるから、就労可能年齢を七五歳までとするのが相当である。
︙
2 被告らの主張
︙
②就労可能期間の終期について
逸失利益は被害者の将来の蓋然性を前提にして算定されるべきものであるから、現実の就労の実態が六七歳を超えてもなお相当高い(少なくともその年齢層の七〇パーセント以上)ということでなければ、現状の六七歳を七五歳まで引き上げる合理性はない。現在においても、高齢者の就労率は決して高くなく、六五歳から七〇歳までの年齢層でさえ半分以下(女医の就労率は更に低い。)と言われている。
全労働者につき六七歳を超えた年齢層の就労比率の検証結果が未だ出ていないのに、医師のみのそれを対象として、七五歳まで引き上げることは公平の理念に反する。
︙
(4) 子の死亡による損害賠償について
① 我が国における従前の裁判実務では、生命侵害による損害賠償請求につき、死者の損害賠償請求権を相続したものとして請求するのが通常である。
本件においても、原告らは、子の死亡による逸失利益等の損害賠償について、死者に生じた逸失利益等を想定し、その相続として計算するいわゆる相続説の考え方に依拠している。
しかしながら、権利能力を喪失している死者にはもともと死亡による損害など生じ得ないから、その相続ということもあり得ない。逸失利益の相続というのは、遺族を救済するための一種の擬制であり、本来は、扶養請求権の侵害による遺族固有の損害賠償請求権ないし慰謝料請求権として構成されるべきものである。また、慰謝料については、民法七一一条という遺族固有の慰謝料請求権を認めた規定があるから、相続という擬制によって遺族の救済をはかる必要はない。
こうした相続の擬制は、子の死亡の場合(いわゆる逆相続の場合)には破綻を来す。すなわち、子の死亡の場合、本来、親については子から受けるべき扶養の分しか財産的損害はないにもかかわらず、子が一生の間に稼ぐはずの総収入を親が相続するというのは、親に実損害以上の超過利益を与えることになる。この超過利益を親に相続として取得させる合理的理由はない。実損害以上の超過利益を相続の擬制によって与えることは心情論はともかく、損害の公平な分担を究極の目的とする損害賠償制度の理念からは望ましいことではない。
このような逆相続の不合理性は、権利能力を喪失している死者自身が損害賠償請求権を取得し、それが相続されると解する相続説(相続構成)を採用するところに端を発しており、その不合理性を抜本的に解消するためには、相続説(相続構成)を改めるべきである。
② 仮に本件について相続説の立場で逸失利益を算定する場合は、逆相続の場合の不合理性等諸般の事情を総合的に考慮し、年収については平成八年賃金センサス第一巻・第一表・産業計・企業規模計・大卒・二五~二九歳の女子労働者の平均賃金を基礎とし、生活費控除率は五〇パーセントとし、稼働期間は二五歳から六七歳までとし、中間利息控除については年五分の新ホフマン方式で計算するのが相当である。
◯は、本件事故当時、学生であって医師ではなく、在籍学部の如何によって年収の基礎につき異なる取扱いをすることは、被害者相互間の公平という観点から相当でない。
︙
第三 争点1(本件事故により◯及び原告らに生じた損害額)に対する判断
︙
(一) 相続構成について
不法行為により被害者が死亡した場合には、被害者の逸失利益、慰謝料等の損害賠償請求権全額を、その相続人が相続により取得することになると解するのが相当である。
ただし、右法律構成は、被告らが指摘するように、被害者が子で親が子の損害賠償請求権を相続により取得することになるいわゆる逆相続の場合には、両親は子よりも先に平均余命が尽きてしまうのが通常であるにもかかわらず、両親の平均余命が尽きた後の子の稼働収入を想定してその逸失利益をも両親が相続する結果となるという理論的矛盾をはらんでいる側面があること自体は否定できない。
以上をふまえつつ、以下、◯の死亡による逸失利益について具体的に検討することとする。
(二) 就労開始時期
前記一2で認定したとおり、◯は、医師になりたいという強い希望を抱き、いったん一橋大学経済学部に入学しながらも医学部を受験し直し、本件事故当時、神戸大学医学部医学科三回生に在学していたところ、◯の神戸大学医学部医学科における成績は、成績が付けられる三四科目のうち「優」が一六科目、「良」が一二科目、「可」が六科目と優秀であったこと、神戸大学医学部出身者の平成九年における医師国家試験合格率は九六・四パーセントと高率であったこと、医学部は、大学の諸学部の中でも、学生の卒業後の進路・職種がほぼ確定している点に特色があることを総合考慮すると、◯は、本件事故に遭わなければ、平成一二年三月に神戸大学医学部医学科を卒業した後、医師国家試験に合格して医師の免許を取得し、同年四月から医師として稼働を開始したであろう蓋然性が極めて高いと認められる。
したがって、◯の死亡による逸失利益の算定に当たって、同人の就労開始時期を平成一二年四月(◯二六歳、死亡後四年目)と認めるのが相当である。
(三) 就労可能期間
厚生省大臣官房統計情報部の「平成八年医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば、平成八年一二月三一日現在、六五歳以上八四歳以下の女性医師は四七三三人おり、そのうち医療施設従事者は四二八六人と全体の約九〇パーセントを占めており、専門職である女性医師の稼働期間は長期にわたり、六七歳以降も就労を継続する蓋然性が高いものと認められる。
したがって、◯の死亡による逸失利益算定に当たっては、前記の逆相続の場合の理論的矛盾点も考慮しつつ、就労可能期間を七〇歳までとみるのが相当である。
解説
日弁連交通事故相談センター「損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)では,就労可能期間の終期については,原則として67歳までとし,67歳を超えるものについては原則として平均余命の1/2を就労可能年数とし,67歳までの年数が平均余命の1/2より短くなるものについては原則として平均余命の1/2を就労可能年数とするとされています。
大阪地裁の基準(大阪地裁民事交通訴訟研究会編著「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準(第3版)」43頁)でも,「労働能力喪失期間の終期は,67歳までとし,年長者については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうとすることを原則としつつ,被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める」とされています。
裁判実務では以上の基準に沿って判断がなされており,若年者について67歳を超える就労可能期間の終期が認められるケースは非常に稀です。
本判決は,成績優秀な医学生について卒業後に医師として稼働する蓋然性が極めて高いと認定した上で,統計から専門職である女性医師の稼働期間は長期にわたり,67歳以降も就労を継続する蓋然性が高いとして,67歳を超える就労可能期間の終期を認定しました。
その上で,「親が子の損害賠償請求権を相続により取得することになるいわゆる逆相続の場合には、両親は子よりも先に平均余命が尽きてしまうのが通常であるにもかかわらず、両親の平均余命が尽きた後の子の稼働収入を想定してその逸失利益をも両親が相続する結果となるという理論的矛盾をはらんでいる側面があること自体は否定できない」と逆相続の理論的矛盾点を考慮した上で,70歳を就労可能期間の終期として認定しました。
本判決は,若年者について67歳を超える就労可能期間の終期が認められた事例として参考になると思われます。