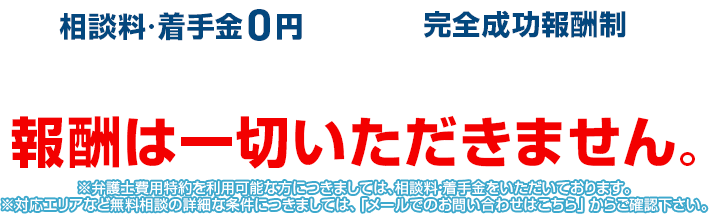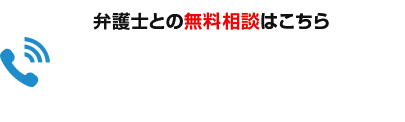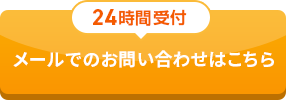脊柱変形の後遺障害
脊柱変形については,以下の表の通りに後遺障害等級が認定されています。
鎖骨や骨盤骨の変形の後遺障害12級5号では,裸体になったとき,変形が明らかにわかる程度のものをいい,変形がレントゲン写真によってはじめてわかる程度のものは該当しないとされていますが,脊柱についてはレントゲン,CT,MRI等で画像を確認して後遺障害が認定されています。
なお,自賠責保険では,後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても,別表第2備考⑥を適用することにより,各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定が行われています。
| 後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
| 別表第2備考⑥を適用 8級相当 |
脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
脊柱変形による労働能力の喪失
脊柱変形は,加害者(保険会社)から労働能力喪失が争われやすい後遺障害の一つですが,6級などの「高度の脊柱変形は,脊椎の骨折という器質的異常により脊椎の支持性と運動性の機能を減少させ,局所等に疼痛を生じさせうる点を考慮すると,原則として喪失率表の定める喪失率を認めるのが相当(片岡武裁判官の講演録「労働能力喪失率の認定について(交通事故による損害賠償の諸問題Ⅲ345頁)」)」と指摘されています。
一方,骨折による変形が軽微な場合には,喪失率表の喪失率をそのまま認めることは相当ではないとの指摘があります(同講演録345頁)。
例えば,同講演録に掲載されている22の裁判例のうち,11の裁判例で喪失率表未満の喪失率が認定され,3の裁判例で喪失期間を分けた上で逓減的に喪失率が認定されています(同講演録343頁)。
そのほか,若年者については,疼痛が次第に緩解して将来喪失する可能性も否定できないから,就労可能年限まで喪失率表の喪失率をそのまま認めるのは相当ではなく,脊椎の器質的損傷はあるものの,若年者であり,脊柱の支持性と運動性の低下が軽微である事案では,労働能力喪失期間を分けた上で,期間毎に喪失率を低減する裁判例(東京地判平成15年2月28日(平成12年(ワ)第19956号)など)の考え方に合理性があると指摘されています。(同講演録345頁)
東京地判平成15年2月28日(平成12年(ワ)第19956号)
(1)労働能力の喪失について
① 原告は,本件交通事故により後遺障害が残り,平成11年5月11日ころに症状が固定し,後遺障害等級併合10級の認定を受けているところ,自賠責保険の実務においては,同10級に該当する者の労働能力喪失率が27パーセントと取り扱われ,また,同12級のそれは14パーセントと取り扱われていることは当裁判所に顕著な事実である。しかし,原告の後遺障害による逸失利益を認定する上での前提となる労働能力喪失率は,同取扱いに拘束されるものではなく,後遺障害の内容と程度,被害者の年齢,性別,職種等を考慮し,個々の後遺障害により労働能力がどの程度喪失されるのかを具体的に検討してなされるべきものである。
② そこで,上記観点から,本件における原告の労働能力喪失の内容を検討するに,原告の後遺障害のうち,労働能力に直接影響があると考えられるのは,右肩関節痛,背部痛及び右下腿のしびれであるから,上記障害の程度につき検討すると,まず,◯医師は,平成12年5月1日付けの診断書において,原告の症状につき,次にような所見を示している。すなわち,Ⅰ胸椎の痛みは,トリガーポイント注射の効果が切れてくると日常生活の際に困難を伴い,ひじ掛けのない場所で前傾姿勢をとることがつらく,また,背骨に負担をかけた時間に応じて痛みが増す,Ⅱ右肩は,腕を挙げると痛みが生じ,右腕が効き腕であることからも日常生活に支障をきたす,Ⅲ上記の症状により原告は前職のオートバイ便に復帰することは困難であり,転職の際にも肉体労働を伴う仕事に就くにはもうしばらくの期間を要するというのである。そして,原告は,右肩関節痛は症状固定後においても回復することなく持続しており,背部痛も背骨が重く熱を帯びたような疼痛があり,同苦痛が生じた時には,その後は身体を休ませる必要がある旨供述している。以上によれば,上記各部位の痛みが原告の稼働能力に支障をもたらすものであることは明らかである。
③ 上記認定事実によれば,右肩関節痛,背部痛及び右下腿のしびれによる障害は,原告の今後の就労先の選択が狭まるほか,職務内容にも制限が伴い,痛みが生じた場合には仕事に集中できなくなり,能率が低くならざるを得ないものと認められ,上記障害が原告の職務遂行に困難を伴うものとなることは明らかである。本件においては,原告は事故後就労していないため,障害が原告の待遇や給与に及ぼす程度は具体的に明らかにはなっていないが,上記認定のとおり,原告には障害及び痛みが認められる以上,今後,相当程度本人の努力によってカバーせざるを得ない面も否定できず,その努力にも自ずと限界があるから,原告が障害により将来の就職,昇給等に不利益な取扱いを受けることは十分予想されるところである。
(2)労働能力の喪失期間について
上記後遺障害は,いずれも神経症状が中心であるが,背部痛は,胸椎骨折により生じているものであり,胸椎の損傷が変形した胸椎のみではなく,その周囲の組織にも及んでいるため,向後持続する可能性が認められるところであり,乙7においても,かなりの期間持続すると思われるとの所見が示されている。
一方で,右肩関節痛は,平成10年12月29日においては「右肩痛良好」とあり,平成11年2月からは右肩鎖関節注射が施行されなくなっていること,骨傷もなく関節可動域制限もないことからすると,疼痛が永続するものとはいえないことも認められる。
以上によれば,上記後遺障害の部位,程度によれば,原告の症状は将来確実に軽減されるものとは予測し難い面はあるものの,原告がまだ若く日常の社会生活を通じて症状の回復,軽減も期待できることを考慮すると,今後,20年間にわたって,労働能力を喪失するものと認められる。
(3)後遺障害による労働能力喪失のまとめ
① 以上を前提として,後遺障害による労働能力喪失率と喪失期間を検討すと,原告の後遺障害のうち,労働能力に直接影響があるのは右肩関節痛,背部痛,右下腿のしびれであり,その後遺障害の部位と程度及び疼痛の残存期間を考慮すると,症状固定時の32歳から少なくとも10年間はその労働能力を20パーセント,その後10年間はその労働能力を14パーセントをそれぞれ喪失するものと認められる。
② もっとも,被告は,その労働能力を5年間にわたり等級表12級の14パーセント喪失するにとどまる旨主張するが,右肩関節痛及び背部痛は,いずれも上肢に残存する障害であるものの,自賠責保険の実務では,上記右肩関節痛及び背部痛は部位を異にすることからすると,それらを総合して考慮するのが相当である。そうすると,原告は,その労働能力を右肩関節痛及び背部痛が残存する10年間については,少なくとも同11級に相当する20パーセント喪失するものと認めるのが相当である。
③ ところで,原告は,右下肢及び左下肢の醜状痕(同14級)も実生活に影響を与えている旨主張するが,右下肢及び左下肢に醜状痕が残存することは,労働能力に影響を及ぼすものとはいえないから,原告の主張は採用できない。